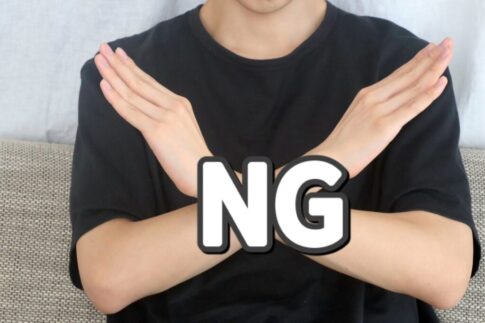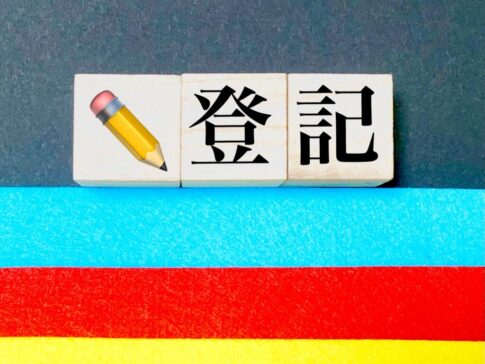皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
「相続放棄」と聞くと、多くの方が「借金を引き継ぎたくない」といったイメージを持つかもしれません。
しかし最近では、価値の低い不動産を相続したくないという理由から、「少額の遺産なら相続放棄を選ぶ」というケースが増えてきています。
そこで本日は、原則「3ヶ月以内」とされている申述期限に注意しながら、相続放棄をスムーズに進めるための具体的な手順について話してまいります。
目次
相続放棄の基本知識
相続放棄とは
相続放棄とは、財産も借金も一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に申し立てることです。
相続放棄が必要になる主なケース
- 親に借金がある
- 遠方の空き家や土地を相続しても管理できない
- 相続人同士でもめたくない
- 被相続人のことを知らない(縁遠い親戚)
相続放棄で知っておくべきこと
- 家庭裁判所で手続きが必要
- 期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」
- 一度放棄すると「取り消し不可」
- 相続放棄をすると「最初から相続人でなかったこと」になる

スムーズに進める!相続放棄の7つの手順
【手順①】亡くなった方の「相続関係」を確認しよう
まずは、最寄りの市町村役場で「戸籍謄本」を取得して、誰が相続人にあたるのかを確認します。
【手順②】遺産の内容(借金や資産)を把握しよう
負の遺産かどうかの判断材料になります。
- 通帳やクレジット明細、借用書などを確認
- 借金の有無が不安なときは、信用情報機関に情報開示請求を行う
- 不動産の所有状況を確認するには、固定資産税通知書を確認するか、最寄りの市町村役場で名寄帳を取得する
【手順③】放棄するかどうかを家族で話し合おう
とくに、兄弟姉妹や親戚がいる場合は、事前に話し合っておくのがベストです。
- 自分だけ放棄すると、他の人に相続が移ります(次順位相続)
- 放棄者が続くと、最終的には遠い親戚まで影響が及びます
- 親族間トラブルを避けるなら「同時に相続放棄する」選択も
【手順④】必要書類を準備しよう
家庭裁判所に提出する主な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所にある様式)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
- 自分(申述人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(各裁判所で異なる)
【手順⑤】家庭裁判所に相続放棄の申述をする
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
- 郵送でも提出可能(事前に裁判所HPで必要事項を確認)
- 約2週間ほどで「受理通知書」が届く
不安な場合は、事前に家庭裁判所の窓口や電話で相談しておくと、手続きがスムーズに進みます。
【手順⑥】申述後は「受理通知」が届くのを待とう
- 家庭裁判所が内容を確認して、正式に受理されると「通知書」が届きます
- 不備があると補正が求められます
通知が届くまで、遺産に手を出さないのが鉄則(遺品整理などは要注意)
【手順⑦】他の相続人に「相続放棄が受理されたこと」を伝えておこう
自分が放棄したことにより、他の人が相続人になります。
- 遺産分割協議の際に「相続放棄通知書」を添えて説明する
- 必要に応じて、書面で通知を出すと親切

まとめ|相続放棄は「3ヶ月以内」に正しい手順で
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 放棄の期限 | 相続開始を知ってから3ヶ月以内 |
| 手続きに必要な場所 | 家庭裁判所 |
| 放棄の影響 | 他の相続人に権利が移る |
| 放棄前後にやってはいけないこと | 相続財産を使う、貸す、移動させる・遺品整理・不動産の売却・名義変更など |
相続放棄は、正しい手順を守れば決して難しい手続きではありません。
ただし、相続放棄は家庭裁判所で一度「受理」された後でも、その後の行動や新たに判明した事実によって、無効と判断される可能性があるため注意が必要です。