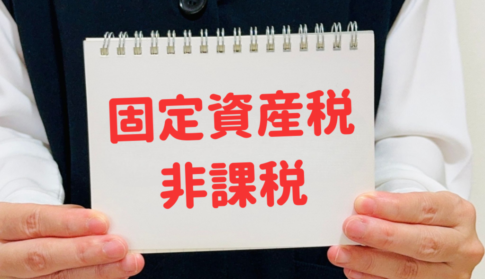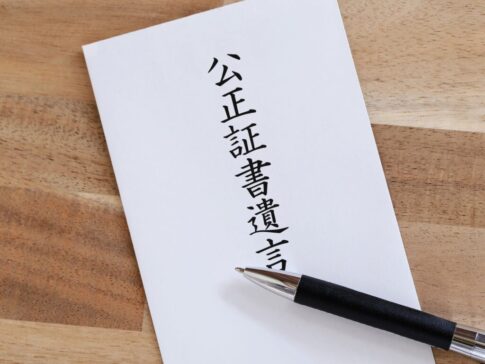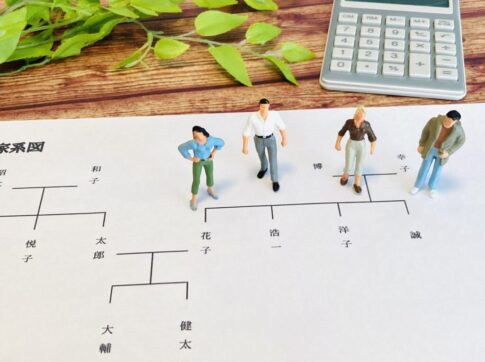皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
家を建てるためには、建築基準法で定められた「接道義務」を満たす必要があります。
つまり、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないというルールです。
しかし、相続した土地や古い住宅地の中には、この条件を満たしていないものが多く見られます。
その場合、「再建築不可物件」とされ、新しく家を建てることができなくなってしまいます。
こうした土地を救済するために設けられているのが、建築基準法43条但し書きです。
そこで本日は、43条但し書きの基本的な意味、2項道路との関係、建築許可が下りる具体的な条件、許可が得られなかった場合のリスクと対策について話してまいります。
目次
43条但し書きとは?【基本の考え方】
43条但し書きの位置づけ
結論から言うと、「43条ただし書き」とは 本来は再建築できない土地でも、一定の条件を満たせば建築を認める救済制度 です。
建築基準法では、原則として建物を建てるためには「幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という「接道義務」がありますが、昔からの細い道や私道に接している土地では、この基準を満たさないケースが多くあります。
そうなると「再建築不可」という扱いになり、次のような問題に直面します。
- 家を建て替えられない
- 売却したくても買い手がつかない
- 金融機関から住宅ローンが下りない
このような土地の活用をまったく認めないと、都市計画や地域の維持にも支障が出るため、特例として設けられたのが「43条但し書き」です。
43条但し書きの適用事例
- 幅が4m未満の2項道路に接している土地
- 農道や里道など、法的には道路扱いされていないが実態的に通路として利用されている道に接する土地
- 公共性を損なわない範囲で例外的に建築を認める必要がある場合
要するに、 「普通はNGだけど、合理性があるなら例外的に建ててもいいよ」という制度 と考えると分かりやすいでしょう。

2項道路と43条但し書きの関係
2項道路とは?
まず「2項道路」について整理しておきましょう。
2項道路とは、建築基準法第42条第2項に基づき「幅4mに満たないが、昔から建物が立ち並んでいる道路で、将来的に4mに拡幅されることを前提に道路とみなされるもの」です。
つまり、現状は幅2〜3mしかない細い道路でも、「将来的にはセットバック(敷地を後退させる)して4m道路にすること」を条件に道路として扱われます。
2項道路に接する土地の問題点
2項道路に面した土地では、以下のような課題が生じます。
- 建て替え時に敷地を道路側に後退(セットバック)させる必要がある
- 道幅が狭いため、消防車や救急車などの進入が難しく、防災面の懸念がある
- 自治体によっては再建築許可に厳しい条件が付けられる
こうした制約をクリアするために登場するのが「43条但し書き」です。
43条ただし書きで救済されるケース
例えば、次のようなケースでは「但し書き許可」が認められ、再建築が可能となることがあります。
- セットバックを実施すれば安全性が確保できる
- 敷地が公園や広場に接しており、実質的に避難経路や防災上の安全性が確保できる
- 道幅が狭いが、隣地との協力で消防活動に支障がない

建築許可が下りるための条件とは?
43条但し書きの許可を得るには、自治体が定める具体的な基準を満たす必要があります。
一般的な条件(自治体によって異なる)
- 防災上の支障がないこと
消防活動や避難に支障がないかを確認。 - 周辺環境に悪影響を与えないこと
隣地の日照・通風、景観に大きな問題がないか。 - 敷地のセットバックが可能であること
将来的な道路拡幅に協力できるかどうか。 - 建物規模や用途の制限
大規模なマンションや商業施設は不可、小規模住宅ならOKというケースが多い。 - 建築審査会の同意
自治体によっては建築審査会での承認が必要。
実務的な流れ
- 事前相談(建築士や不動産会社を通じて役所に確認)
- 設計図面と併せて申請
- 審査(防災・都市計画・周辺住民への影響などをチェック)
- 許可が下りれば建築可能

許可が得られない場合のリスクと対策
許可が下りなかった場合のリスク
- 再建築不可となり、建て替えができない
- 売却しようとしても買い手が見つからない
- 負動産となる可能性が高い
対策
- リフォームやリノベーションで既存建物を活かす
- 隣地の一部を購入して接道義務を満たす
- 接道要件を満たすことのできる土地の所有者に引き取ってもらう
- 無償譲渡や相続土地国庫帰属制度による処分を検討する

まとめ|43条ただし書きは「再建築不可救済のカギ」
「43条但し書き」とは、再建築不可に見える土地でも例外的に建築を認めるための制度です。
とくに「2項道路(幅員4m未満の道路)」に接する土地では、この制度の有無が「家が建てられるかどうか」を左右する非常に重要なポイントになります。
ただし、許可が下りるかどうかは各自治体の判断によるため、事前に建築士や不動産会社へ相談し、行政との調整を進めることが不可欠です。