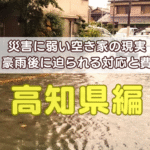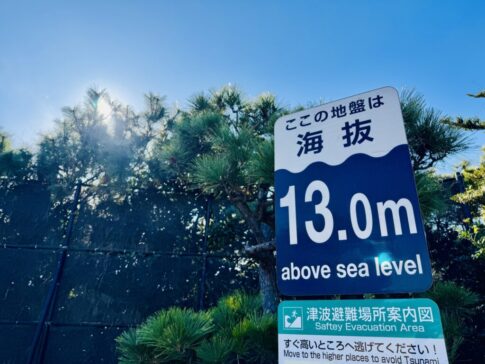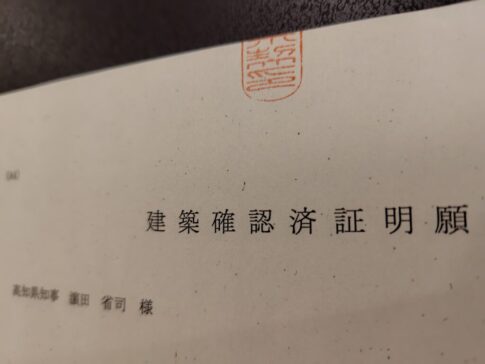皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
近年、人口減少と高齢化が進む日本では、「コンパクトシティ」という言葉が注目を集めています。
聞き慣れない方もいるかもしれませんが、これは「住民が分散して住むのではなく、町をギュッと集約して暮らす」ことで、限られた財源の中でも生活に必要なインフラや福祉サービスを維持していこう、という考え方です。
「昔の暮らしに戻す」というと、過疎地を切り捨ててしまうように聞こえるかもしれません。
ですが本来の目的は切り捨てではなく、 増税することなく、今の社会保障やインフラを維持しながら“住みやすい環境”を目指すこと にあります。
そこで本日は、コンパクトシティの可能性について話してまいります。
目次
なぜコンパクトシティが必要なのか?
1. 人口減少と広がりすぎた都市
戦後の高度経済成長期、日本各地の都市は拡大し、郊外にも住宅地がどんどん広がりました。
しかし現在は少子高齢化が進み、人口は減少しています。
にもかかわらず、インフラ(道路・上下水道・電気・病院・学校)は広範囲に維持し続けなければならず、自治体財政は大きな負担を抱えています。
2. サービス維持のための集約
住民がまとまって暮らせば、医療・介護・公共交通などを効率よく提供できます。
高齢者や子育て世代にとっては、徒歩圏内に病院や学校、日用品を扱うスーパーなどの生活必需施設がそろっていることが、大きな安心につながります。

「昔に戻す」とはどういうことか
かつての日本では、町の中心に役場や商店街、学校、病院があり、その周りに住民が暮らすのが一般的でした。
一方、農村は農業に特化し、まとまりある集落を形成していました。
コンパクトシティとは、この「昔の形」を現代版に再構築すること とも言えます。
ただ単に「広がりすぎた居住地を縮小する」だけではなく、最新のテクノロジーや持続可能な仕組みを取り入れながら、効率的な生活圏を取り戻します。
農村の役割と効率的な農業への転換
農村地域では、過疎化により耕作放棄地が増えています。
これを解決するためには、小規模に分散した農地を集約し、 効率の高い農業を営める体制づくり が欠かせません。
- 農地の集約による大規模農業の推進
- ICT・AIを活用したスマート農業
- 農業法人や担い手による効率的で収益性の高い経営
こうした施策により、農村は「生活の場」よりも「食料供給の拠点」として強みを発揮できます。

コンパクトシティと農村がつながる未来
都市は「住みやすさ」を、農村は「生産性」を高め、それぞれの強みを生かすことが重要です。
そのためには、都市と農村を結ぶ交通・物流のネットワークも不可欠です。
- コンパクトシティで暮らしの基盤を維持
- 農村で効率的な農業を展開
- 都市と農村が相互に支え合う仕組みをつくる
このサイクルが実現すれば、日本の将来は単なる「縮小」ではなく、食料自給率の向上と安定したGDP成長につながる持続可能な最適化を実現できます。

まとめ|切り捨てではなく持続可能な最適化
「居住地を昔に戻す」とは、決して過疎地を切り捨てる話ではありません。
町を集約することで、増税することなくインフラや社会保障を守り、農村は効率的な農業で未来を支える。
これが本来のコンパクトシティの目的です。
人口減少という避けられない課題に対して、「どう縮小するか」ではなく、「どう最適化するか」を考えること。
それこそが、人口減少が進む高知県における今後のまちづくりや農村政策に、まさに求められている視点であると考えます。