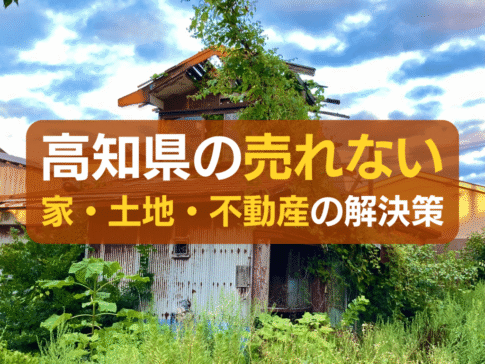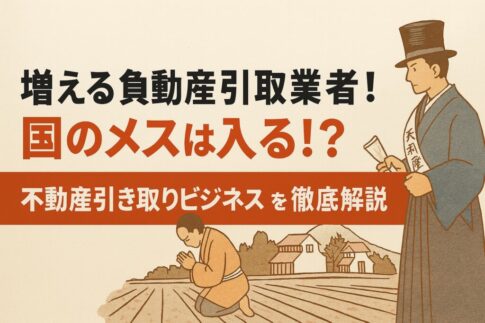皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
「生命保険には500万円の非課税枠があるから、税金もかからずスムーズに渡せる。だから相続トラブルの心配もないよね?」そう考えている方は、要注意です。
生命保険の非課税枠と、遺留分の問題はまったく別の話です。
この2つを混同してしまうと、想定外の“相続トラブル”に巻き込まれるリスクがあります。
そこで本日は、生命保険の「500万円非課税枠」と「遺留分」の正しい関係について話してまいります。
目次
生命保険の「500万円非課税枠」とは何か?
生命保険の500万円非課税枠とは、「法定相続人の数 × 500万円」までの保険金が相続税の課税対象から除かれるという税金上の特例です。
これは、相続人の生活保障などを考慮し、国が定めている制度です。
例えば、夫が亡くなって妻と子ども2人が相続人なら、500万×3=1,500万円までは非課税になります。
- 相続人:妻・長女・次女の3人
- 夫が死亡時に加入していた生命保険の受取人:長女のみ
- 保険金の額:1,200万円
この場合、1,500万円までは非課税枠内となり、相続税の対象にはなりません。

「遺留分」とは?保険金にも影響する?
遺留分とは、法定相続人が最低限もらえると法律で定められている取り分のことです。
そして、生命保険の保険金も、状況によっては遺留分の計算に入ることがあります。
民法では、遺言や贈与であっても、他の相続人の遺留分を侵害してはならないとされています。
例えば長女に全額保険金が支払われた場合、次女が「自分の遺留分が侵害された」として、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
- 被相続人:母
- 相続人:長女・次女の2人
- 保険金受取人:長女のみ2,000万円
- 他の財産:ほぼゼロ
この場合、次女には本来遺留分として全体の1/4(=500万円)程度が認められる可能性があります。
保険金が特定の人に集中していると、裁判では「特別受益」とみなされて遺留分の対象になるケースもあります。
たとえ「保険金は受取人固有の財産」とされていても、遺留分を侵害するほど偏っていれば、争いに発展する恐れがあります。
「非課税だから遺留分は関係ない」は危険
「非課税枠内の生命保険金だから安心」「税金がかからない=法的にも問題ない」という考え方は危険です。
非課税と遺留分はまったく別の制度です。
500万円控除は、税法上の仕組みです。一方、遺留分は民法に基づいた“財産の分け方”のルールです。
この2つは法律の根拠も考え方も別物で、税金がかからなくても、相続人から「不公平だ」と訴えられるリスクはゼロにはなりません。
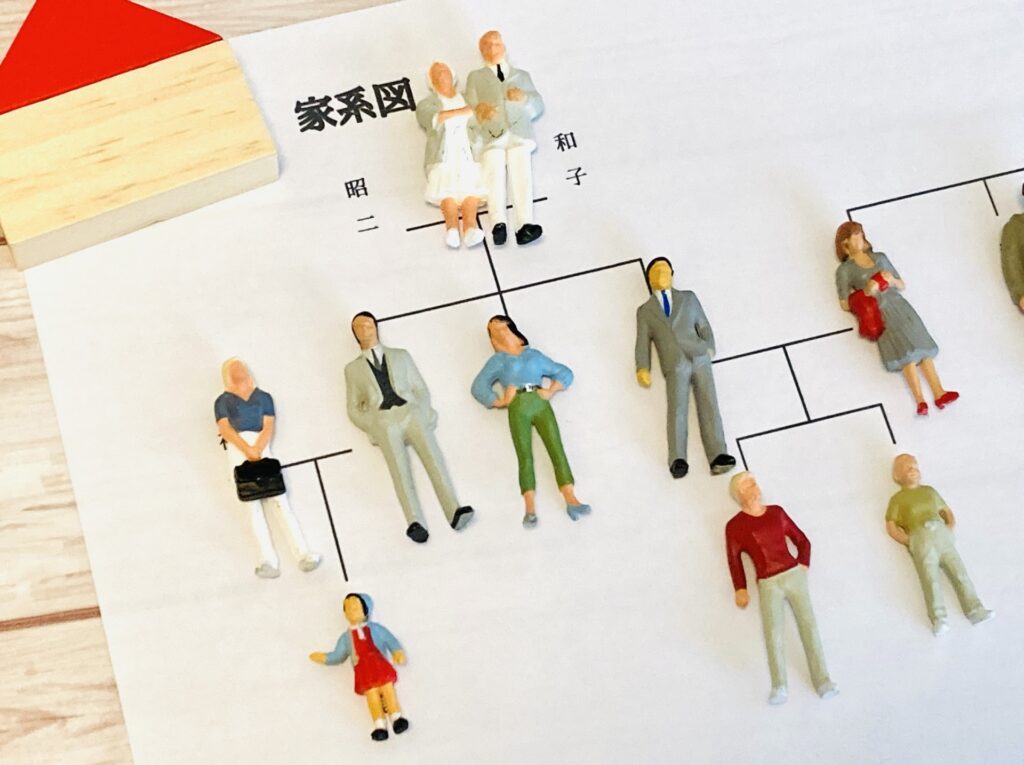
トラブル回避のためにできる対策とは?
生命保険を相続対策に使うなら、税金と法律の両面から設計することが大切です。
家族の「感情」と「納得感」も視野に入れておく必要があります。
たとえ法律的に問題がなくても、相続では「気持ちの不公平感」から争いが生まれます。
だからこそ、保険金の設定だけに頼らず、遺言書の作成や家族会議による説明が重要になります。
トラブルを回避する具体策
- 保険金を一人に集中させない(バランスを考える)
- 受取人を複数に分ける or 現金・不動産との調整を行う
- 公正証書遺言を作成して「なぜそうしたか」を明記
- どうしても特定の人に財産を渡したいと考える場合は、別の方法を考える
まとめ|生命保険の非課税枠と遺留分は“まったく別物”
- 生命保険の500万円控除はあくまで「税金上の優遇措置」
- 遺留分は「相続人の取り分」を守る法律上の制度
- 非課税枠内であっても、偏った配分は遺留分侵害請求の対象になり得る
- 保険金受取人の設定には十分な配慮が不可欠