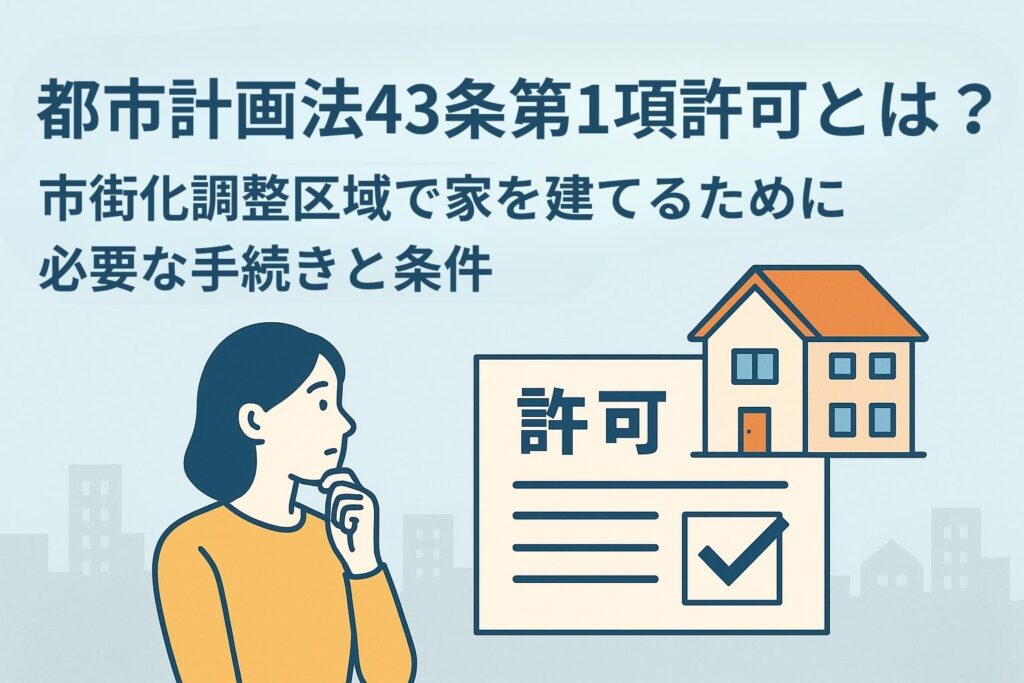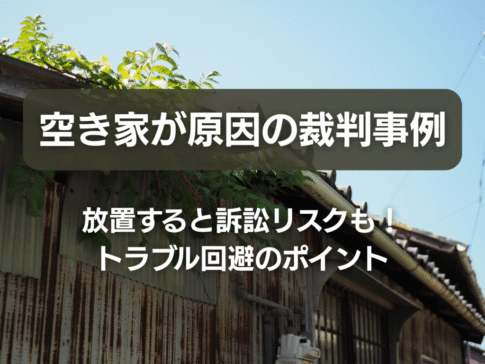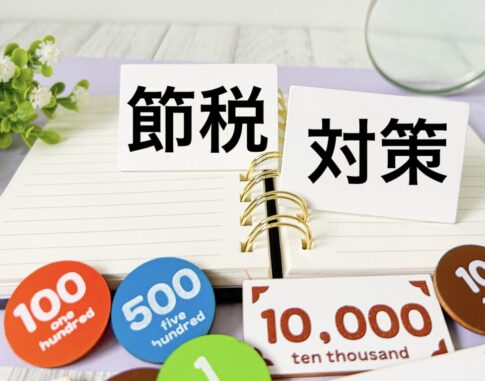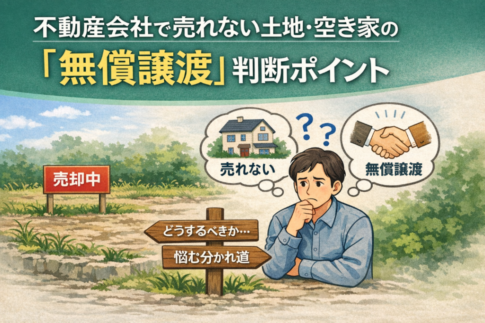皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
「親から土地を相続したけれど、市街化調整区域だから家が建てられないと言われた…」
「売却を検討しているが、建てられない土地だと買い手がつかないのでは?」
市街化調整区域にある土地を相続した方や活用を検討している方にとって、「都市計画法43条第1項許可」は避けて通れないテーマです。
そこで本日は、その意味や取得条件、売却への影響について話してまいります。
目次
都市計画法43条第1項許可とは?
都市計画法第43条は、市街化調整区域などの「原則として建築できない土地」で例外的に建築を認める制度を定めています。
- 第1項:建築を行う場合は都道府県知事(または市町村長)の「許可」が必要
- 第2項:農業用施設など一部の行為は「許可不要」
つまり「43条第1項許可」とは、通常は家を建てられない市街化調整区域で、特別に建築を認めてもらうための正式な許可を指します。
不動産業界では一般的に「43条許可」と呼ばれますが、正式には「都市計画法43条第1項許可」が正しい名称です。

相続土地で43条第1項許可が必要になるケース
相続した土地が市街化調整区域にある場合、次のような場面で43条第1項許可が必要となります。
- 相続した古家を解体し、新しい家を建てたい
- 相続土地に新築住宅を建てたい
- 子どもや親族に土地を譲り、居住用に活用してほしい
- 売却を予定しており、買主が住宅を建てたいと考えている
このように、許可が取れるかどうかは「自分が住む」だけでなく「売れるかどうか」にも大きく関わります。
許可を得るための主な条件
43条第1項許可を得るには、以下の条件が重視されます。
- 周辺環境との調和
既存の集落や住宅地と一体性があるかどうか。 - インフラの整備状況
道路、上下水道、排水などが整っているか。 - 公益上の支障がないこと
農業振興、防災、自然保護などの観点から問題がないか。 - 建て替えや居住継続のケース
「親が住んでいた家を建て替える」など、既存利用を引き継ぐ場合は認められやすい。

申請の流れ
43条第1項許可の一般的な流れは次の通りです。
- 役所への事前相談
市町村の都市計画課に相談し、可能性を確認。 - 必要書類の準備
- 申請書
- 位置図・配置図
- 建築計画の図面
- 理由書(なぜ建てる必要があるのか)
- 役所に申請 → 都市計画審議会などで審査
- 許可通知を受け、建築確認申請へ進む
期間と費用の目安
- 期間:2〜5カ月程度(自治体・案件により変動)
- 費用:
- 行政手数料:数万円
- 専門家に依頼する場合:10〜30万円程度(書類作成・調整費用など)

売却への影響
相続土地を売却する際、43条第1項許可の有無は価格や成約スピードに大きな影響を与えます。
- 許可がない場合 → 「建てられない土地」と見なされ、需要が低く売却が難しい
- 許可取得済みの場合 → 「建築可能な宅地」として販売でき、買主は安心して購入を検討できる
また、買主が自ら許可を申請するケースもありますが、「許可が下りる見込みがあるか」を事前に確認しておくことが重要です。
専門家に相談すべき理由
43条第1項許可は、役所との調整や資料準備が複雑で、個人で申請するには専門的な知識が求められます。
- 許可が下りる条件を満たしているかどうかの判断
- 図面や理由書の作成
- 農地転用・境界確定など関連手続きとの調整
これらを考えると、行政書士・建築士・不動産会社と連携して進めるのが安心です。

まとめ|市街化調整区域の売却・活用は「43条第1項許可」がカギ
- 都市計画法43条第1項許可とは、市街化調整区域で建築を例外的に認めてもらう制度
- 相続した土地に住宅を建てる・建て替える・売却する場合に大きく関わる
- 許可の有無で土地の価値は大きく変わる
- 期間や費用はかかるが、専門家と連携することでスムーズに進められる
相続した市街化調整区域の土地を売却するにも活用するにも、まずは「43条第1項許可」の可能性を確認することが第一歩です。