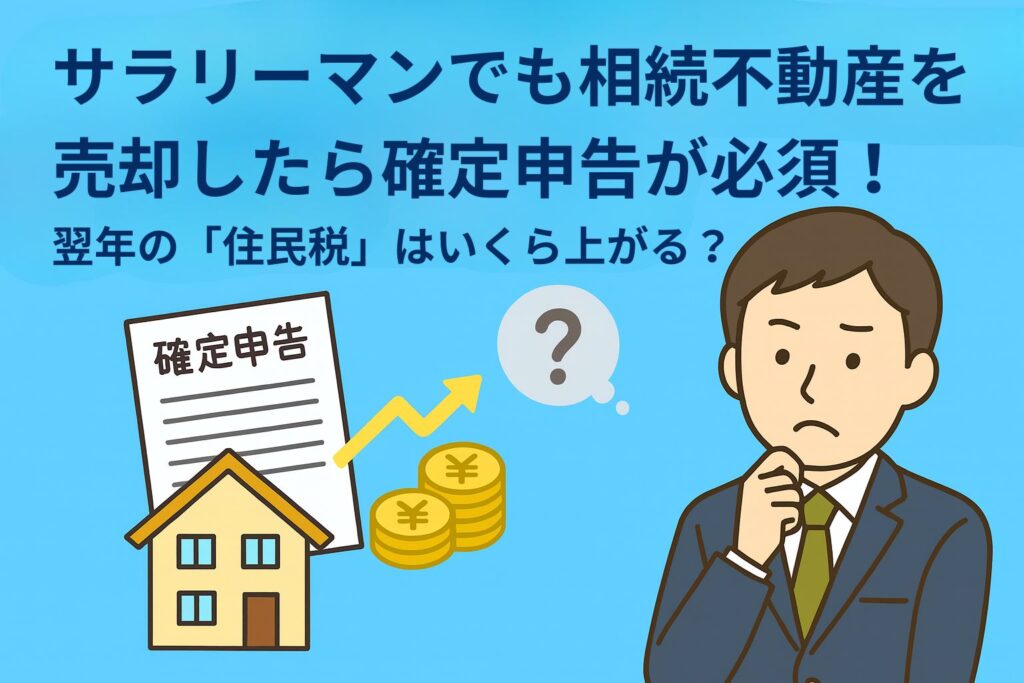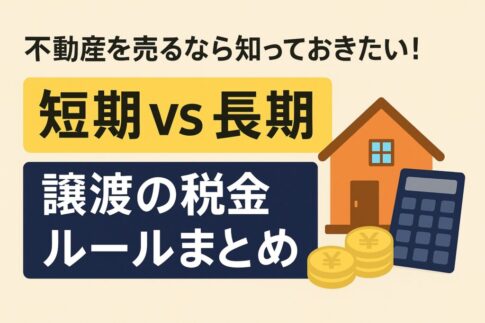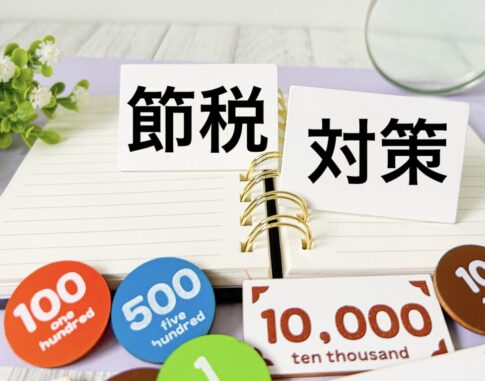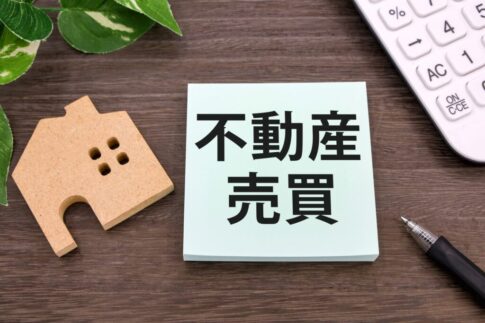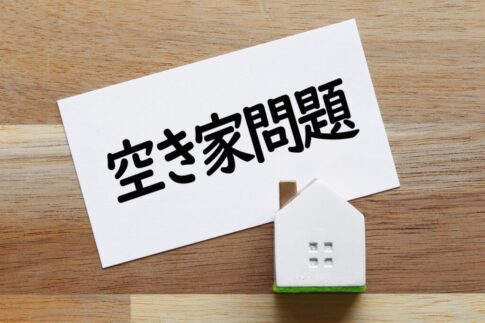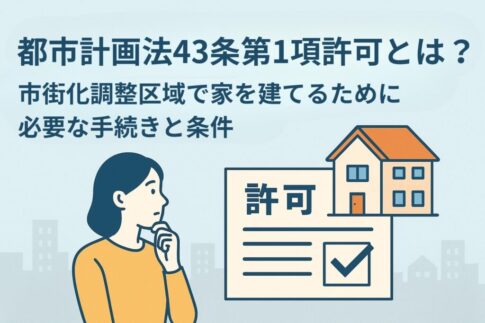皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
サラリーマンの給与所得は会社が年末調整で手続きしてくれるため、普段は自分で申告することはありません。
しかし、相続した不動産を売却して利益が出た場合は、年末調整では処理できないため、自分で確定申告を行う必要があります。
しかも、その影響は翌年の住民税に直結し、「思った以上に税金が増えた」と驚く方が多くなります。
そこで本日は、
- サラリーマンが相続不動産を売却した場合に確定申告が必要となるケース
- 翌年の住民税がいくら上がるのか
- 節税に役立つ特別控除や軽減税率
について話してまいります。
目次
サラリーマンは自分で確定申告が必要なのか?
不動産の譲渡所得は自分で確定申告
会社員の給与所得は年末調整で処理されますが、不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」に分類されます。
この「不動産譲渡所得」は年末調整では処理されないため、自分で確定申告を行う必要があります。
相続不動産の売却益は課税対象
相続の時点で相続税が発生しない場合でも、その不動産を売却して利益(譲渡所得)が出れば課税されます。
譲渡所得税は以下の式で計算されます。
譲渡所得税 = 譲渡価格(売却額)-(取得費+譲渡費用)
- 取得費:被相続人が購入したときの代金や建築費
- 譲渡費用:仲介手数料、測量費、登記費用など
譲渡所得が発生した際には、確定申告が必要です。
※給与所得者の副収入に適用される「20万円ルール」は、不動産の譲渡には当てはまりません。

翌年の住民税はどう上がる?
住民税は前年の所得で決まる
住民税は前年の所得をもとに翌年6月から課税されます。
つまり、2025年に不動産を売却すれば、その譲渡益に対する住民税は2026年6月以降に請求されます。
住民税の税率は5%または9%
不動産譲渡所得に対する税率は以下の通り。
- 住民税:長期譲渡5%(所有期間5年超)/短期譲渡9%(所有期間5年以下)
例:不動産譲渡所得1000万円×5%(長期譲渡の税率)→ 住民税だけで50万円の負担。
サラリーマンでも「普通徴収」で納付
給与から天引きされる住民税(特別徴収)とは別に、不動産売却益にかかる住民税は「普通徴収」で課税されます。
市区町村から届く納付書を使い、年4回に分割、または一括で自分で納付するのが一般的です。
サラリーマンが知っておくべきポイント
副業ではなく「譲渡所得」
不動産売却で得た利益は副業ではなく「譲渡所得」に区分されます。そのため、会社に副業として報告が行くことはなく、売却益が会社に直接知られることもありません。
まとまった住民税請求が翌年に届く
給与所得と別枠で課税されるため、住民税が前年の2倍以上に膨らむこともあります。
「資金を使い切ってしまい払えない」という事態を避けるため、税金分を確保しておくことが必須です。
確定申告の流れ
- 源泉徴収票(給与分)を準備
- 不動産売却の契約書や仲介手数料の領収書を用意
- 被相続人が購入したときの売買契約書や領収書を用意
- 確定申告書を作成(e-Taxも利用可能)
- 税務署へ提出
- 市区町村が住民税を計算 → 翌年に納付書が届く
※取得費を証明できない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費(5%ルール)」が適用されます。
節税に役立つ特例と対策
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除され、所得税・住民税が大幅に軽減されます。
居住用財産の3,000万円特別控除
被相続人が亡くなる前に住んでいた家を、相続人が一定期間内に売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。
空き家特例と似ていますが、条件が異なります。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
都市計画区域内にある低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得から最大100万円まで控除できる制度です。
相続不動産の中でも使われていない空き家や空き地などが対象になります。
長期譲渡の軽減税率
所有期間が5年を超えていれば、所得税15%+住民税5%に軽減。
赤字でも確定申告を
相続不動産を売却して赤字(譲渡損失)になった場合でも、申告をしなければその損失は反映されません。
確定申告をすることで給与所得などと損益通算でき、翌年以降の税負担を減らす効果が期待できます。
翌年の住民税に備えた資金計画
- 売却益の税金は、売却代金から確保しておく(長期譲渡で約20%・短期譲渡で約40%)
- 住民税は一括または4回に分けて支払う
- 事前に税理士に相談すれば、節税を含めてシミュレーション可能
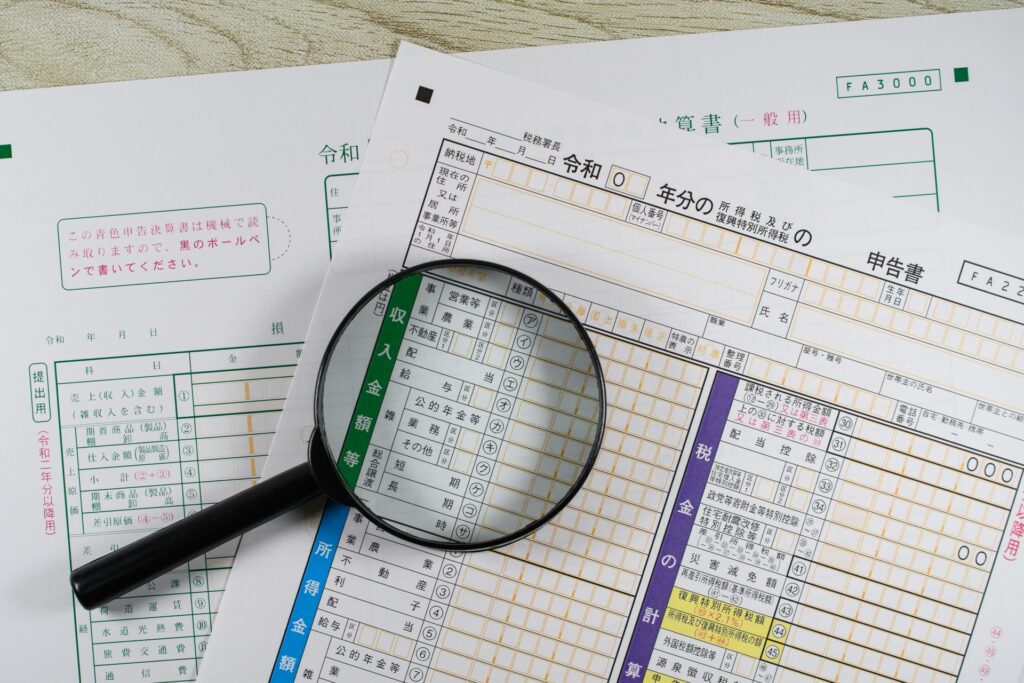
まとめ|サラリーマンも相続不動産を売却したら税金対策が必須
サラリーマンでも、相続不動産を売却すれば自分で確定申告が必要です。
しかもその影響は翌年の住民税に反映され、想定以上の負担になるケースも多くなります。
特別控除や軽減税率を活用しつつ、売却代金の一部を必ず税金分として残しておくことが大切です。
補足すると、利益が出ていない場合はいくらで売却しても確定申告は不要です。
ただし、特別控除を利用する際には申告が必要です。
利益が出ていないのに税務署から「お尋ね」が届いた場合でも、届いたお尋ねの内容に従って回答すれば問題ありません。