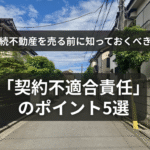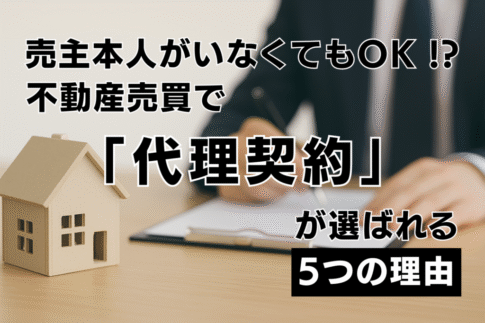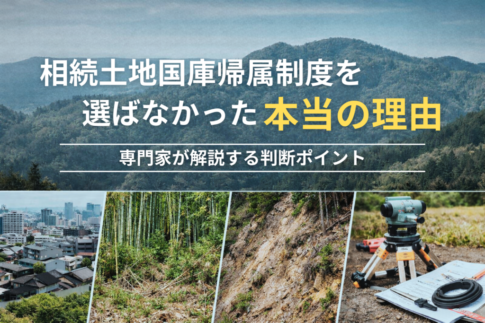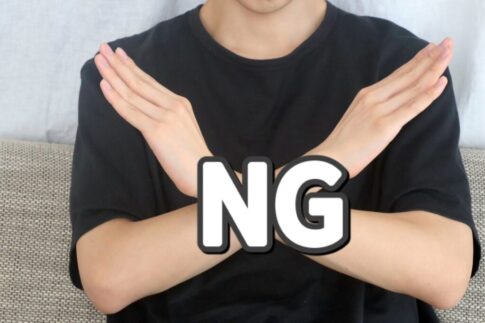皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
『相続した引き取り手のいない土地』——そんな相続人の悩みを解消するために始まったのが、土地を国に返すことができる 相続土地国庫帰属制度 です。
条件を満たせば国に土地を引き取ってもらえる便利な制度ですが、利用者が増えると、ほかの土地の固定資産税が上がるのではないかという疑問も生まれます。
なぜなら、地方自治体の自主財源の約半分を固定資産税が占めており、土地が国に移れば大きな税収減につながるからです。
近年では、人口減少による税収の落ち込みや、高齢化に伴う社会保障費の増加、さらに老朽化したインフラや公共施設の維持・更新にかかる費用が重くのしかかり、多くの地方自治体が財政難に直面しているというニュースが目立つようになっています。
では、相続土地国庫帰属制度によって減少した地方自治体の固定資産税収を、国が補填してくれるのでしょうか?
そこで本日は、相続土地国庫帰属制度の仕組みから税金への影響、そして将来展望について話してまります。
目次
相続土地国庫帰属制度とは?
制度の目的
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月に始まった新しい仕組みです。
目的は「誰も使わない土地を国が引き取ることで、管理不全や空き家・荒廃地の問題を防ぐ」ことにあります。
これまで不要な不動産から逃れるには相続放棄しか手段がありませんでしたが、この制度が導入されたことで、不要な不動産を手放す“出口”が増えました。
利用できる条件
ただし、国が無条件で土地を引き取るわけではありません。条件としては以下のようなものがあります。
- 相続した土地であること
- 建物が残っていない更地であること
- 土壌汚染や崩壊の恐れがないこと
- 管理が極端に難しい土地でないこと
- 土地に関するトラブルや争いがないこと
- 一定の負担金を納めること
つまり、すべての土地が対象ではなく、利用できる人は限られます。
それでも「持っているだけで税金や管理責任がかかる不動産」から解放される可能性がある点で注目されています。
制度のメリット
この制度の最大のメリットは「固定資産税や管理責任から解放される」ことです。
例えば、誰も住まなくなった実家の土地を相続し、固定資産税や管理費を支払い続けるよりは、国に引き取ってもらうほうが安心だと考える人が増えています。
加えて、空き地や空き家が管理されずに放置されると近隣の景観や治安に悪影響を与えるため、社会的にもプラスの効果があります。
制度のデメリット
一方で、条件を満たすために建物の解体が必要だったり、負担金がかかったり、土地の状況によっては申請が通らない場合もある点はデメリットです。
現状の利用状況
制度が始まったばかりのため、帰属件数は1,871件(2025年7月31日現在)とまだ少数です。
しかし今後「空き家問題」や「相続問題」が深刻化するにつれて、利用希望者が増えることは確実です。
そのとき、固定資産税への影響が浮かび上がってきます。

制度が普及すると固定資産税が上がる可能性はあるのか?
結論から言うと、相続土地国庫帰属制度が普及すれば、固定資産税が上がる可能性は否定できません。
その理由を具体的に話してまいります。
固定資産税は市町村の大切な収入源です。
土地や建物から得られる税収は、国からのひも付き財源とは異なり、自由に住民サービスに充てられます。
しかし、土地が国に帰属すると課税対象から外れるため、自治体の収入は減少します。
その穴を埋めるため、残された土地や建物に対して課税強化が行われる可能性もあるのです。
とくに考えられるのは、以下の2点です。
- 特例縮小や都市部・市街地の課税強化
国庫帰属件数が増加すると、税収不足を補うために「小規模住宅用地の特例」や「固定資産税の軽減措置」が縮小されるリスクがあります。その結果、個人が所有する残された土地への課税が厳しくなるシナリオが想定されます。 - 高齢化と人口減少による福祉費の増大
地方自治体は介護や医療、福祉にかかる費用が年々増加しています。労働人口が減って税収が減る一方で高齢者は増えるため、財政はさらに厳しくなります。この負担をまかなうために、固定資産税を引き上げる流れは十分に考えられます。
例えば、ある町で10人が不要な宅地を国に帰属させたとします。
これまでその宅地から年間30万円の固定資産税が入っていたとすると、国庫帰属によりその収入はゼロになります。
その分の穴埋めをするには、他の住民からの税収を増やすか、サービスを削減するしかありません。
結果として「固定資産税の税率引き上げ」や「課税評価額の見直し」が検討される可能性が高くなります。
さらに都市部では、マンションや商業地など「需要の高い土地」に課税強化が進むケースも予想されます。
これは税収を効率的に確保するための現実的な手段です。
また、地方の小さな自治体では老朽化したインフラの更新や社会保障費の急増により、これまで以上に税金の引き上げを検討せざるを得ない状況が生まれるでしょう。
つまり、制度は土地を手放す個人にとっては助かる一方で、地域全体では税負担がシフトするリスクをはらんでいます。
とくに、特例縮小や需要の高い土地の評価額見直しを背景に、固定資産税の負担が増す可能性は現実味を帯びています。
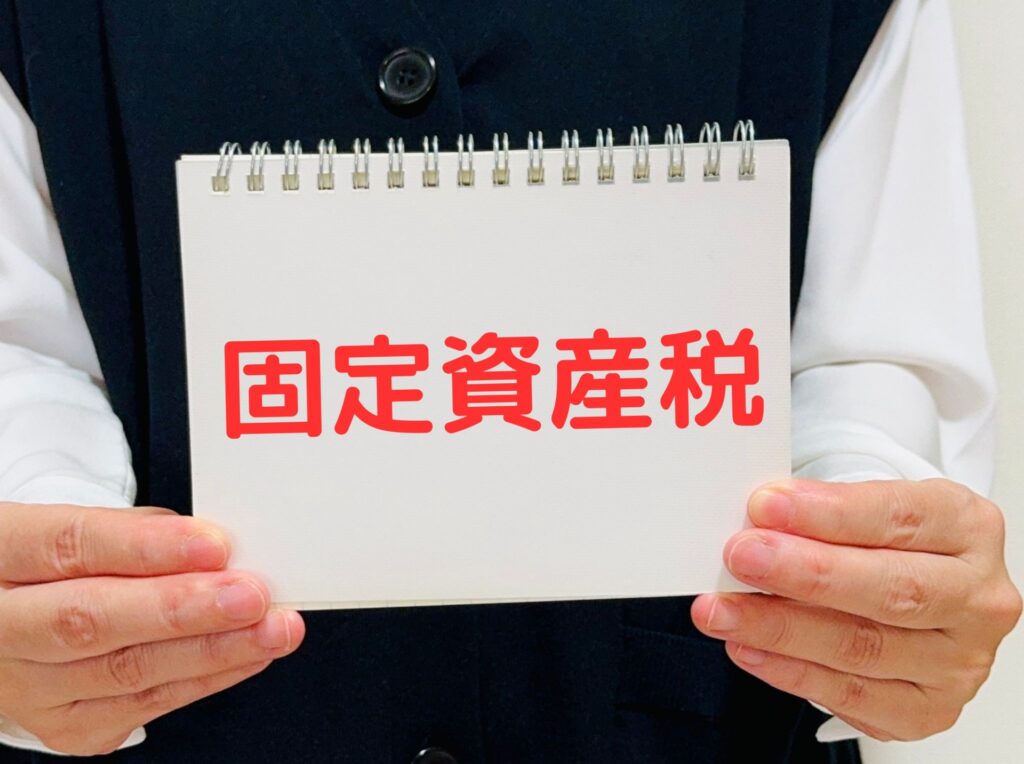
将来的にどんな影響が考えられるのか
1. 税収確保をめぐる自治体の動き
自治体は国庫帰属による税収減を補うため、税制改正や新たな課税方式を模索するでしょう。
都市部では土地の評価額を上げる動き、その他エリアでは特例や軽減税率の縮小をする動きが強まると考えられます。
2. 国庫帰属制度の見直し議論
普及が進むにつれて、制度そのものの見直しも議論されるでしょう。
負担金の増額、対象範囲の縮小、あるいは自治体と国の負担金分担の再調整などが検討される可能性があります。
3. 個人への影響
不動産を所有する負担は今後ますます重くなります。
地方で需要の高い土地は年々減少しており、人口減少という根本的な課題とも直結しているため、簡単に解決することはできません。

まとめ|固定資産税の負担増は十分に起こり得る
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放せる画期的な制度ですが、その一方で『固定資産税の負担増』というリスクも伴います。
特例や軽減税率の縮小、需要の高い土地への課税強化など、将来的な増税シナリオは十分に考えられます。
だからこそ、自分の所有する土地を今後どう扱うかを早めに検討することが重要です。