皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
相続によって不動産を取得すると、必ずついてまわるのが 固定資産税 です。
とくに空き家や使い道のない土地を相続した場合、利用価値がないのに毎年課税されるため、相続人同士でトラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで本日は、相続した空き家・土地に関わる固定資産税の基本ルールと、実際によくあるトラブル事例、さらに回避のためのポイントについて話してまいります。
目次
固定資産税は誰が払うのか?
固定資産税は、その年の 1月1日時点の所有者 に課税されます。
つまり、相続登記が済んでいなくても、亡くなった方(被相続人)の名義のままであれば、いったん相続人全員に納税義務が生じる形になります。
ただし実務上は以下のように整理されます。
- 単独相続の場合:名義変更後、その不動産を相続した人が納税
- 共有相続の場合:共有者全員が連帯して納税義務を負う
- 未登記の場合:市町村は「代表相続人」を指定して納税通知書を送付するケースが多い
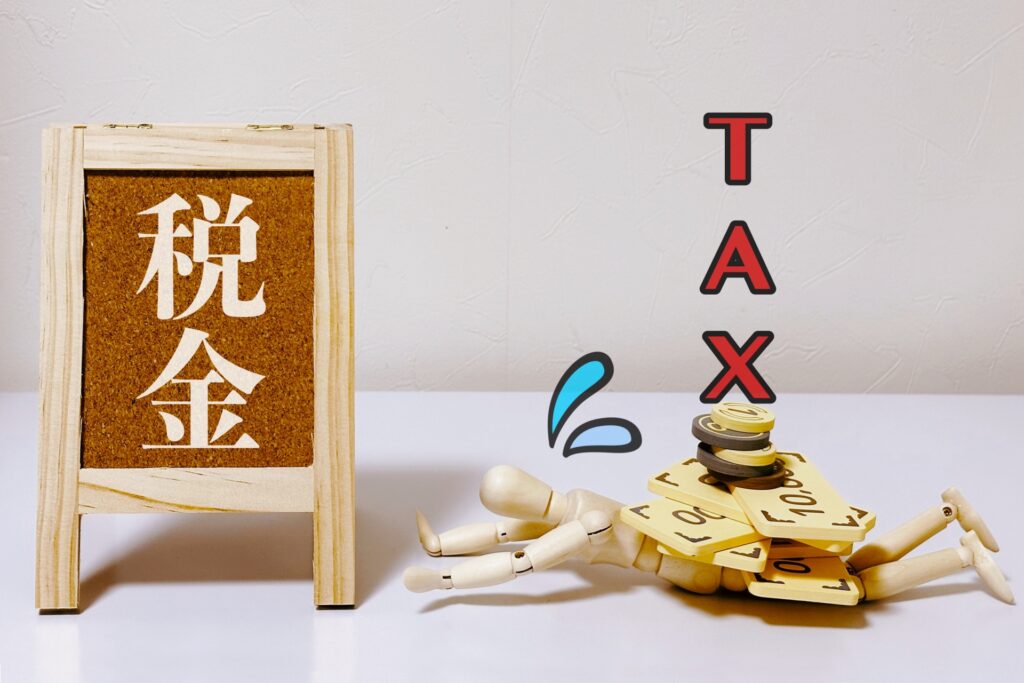
相続した不動産で起こりがちな税金トラブル事例
1. 兄弟で共有名義にしたが、誰も払わない
親の空き家を兄弟3人で共有相続。固定資産税は全員の負担ですが、誰も積極的に払おうとせず、滞納が続いて延滞金が発生。最終的に自治体から差し押さえを受けた事例があります。
2. 相続登記を放置したまま代表者だけに請求
名義変更をせずにいたため、市役所から代表相続人1人にだけ納税通知書が届くケース。支払いを続けていた代表者が「自分ばかり負担して不公平だ」と兄弟と揉める例が多発しています。
3. 相続放棄をしたのに請求が届いた
「相続放棄」をすれば固定資産税も払わなくていいのが原則です。しかし、放棄の手続きを裁判所で正式に行っていなかったため、他の相続人と一緒に課税対象とされてしまった事例もあります。
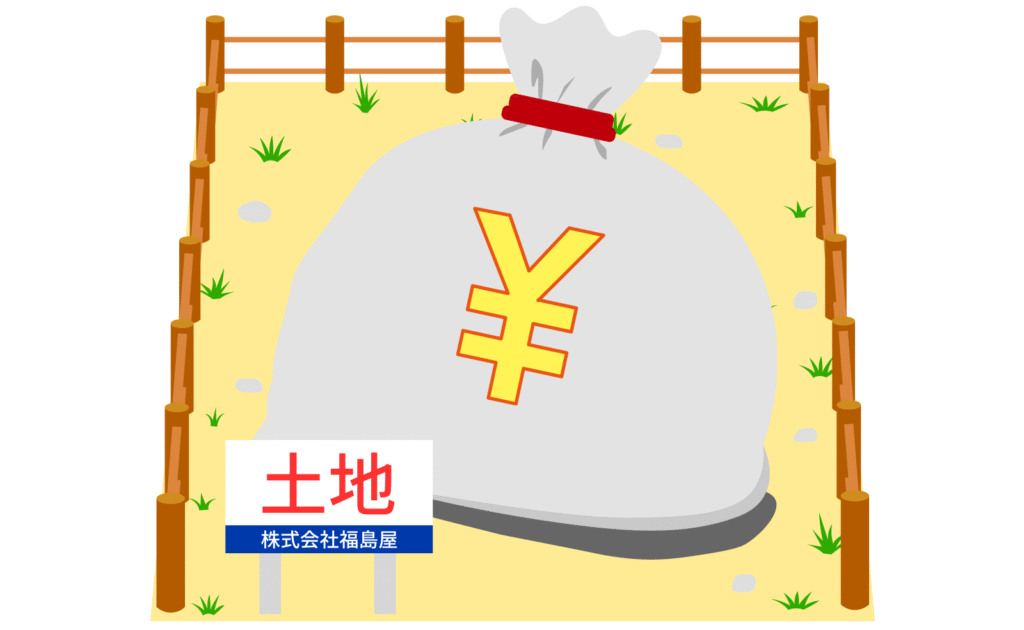
トラブルを避けるためのポイント
- 相続登記を早めに行う
誰が所有者かを明確にすることで、納税義務の所在もはっきりします。 - 共有よりも単独相続を優先
共有はトラブルの元。できれば話し合いで1人が取得し、他の相続人には代償金を支払う方法を検討しましょう。 - 相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きする
口頭や合意だけでは無効。正式な放棄手続きをしておかないと、放棄が認められず負担を背負うことになります。 - 使わない不動産は早めに処分・活用を検討
売却や賃貸のほか、無償譲渡や「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、税金負担を減らす選択肢があります。

まとめ|固定資産税の支払いは、不公平が生じやすい仕組み
固定資産税は、不動産を相続した瞬間から避けて通れない「維持コスト」になります。
相続人が国内のどこに住んでいても、自治体は戸籍や住民票の情報をもとに請求先を特定し、固定資産税を課税してきます。
海外に居住している場合でも同様で、納税義務は免れません。
とくに使い道のない土地では、相続人同士での負担割合をめぐって揉めやすく、放置すれば滞納・差押えにまで発展します。
相続登記や不動産の処分は、適切なタイミングを見極めることが重要です。


































