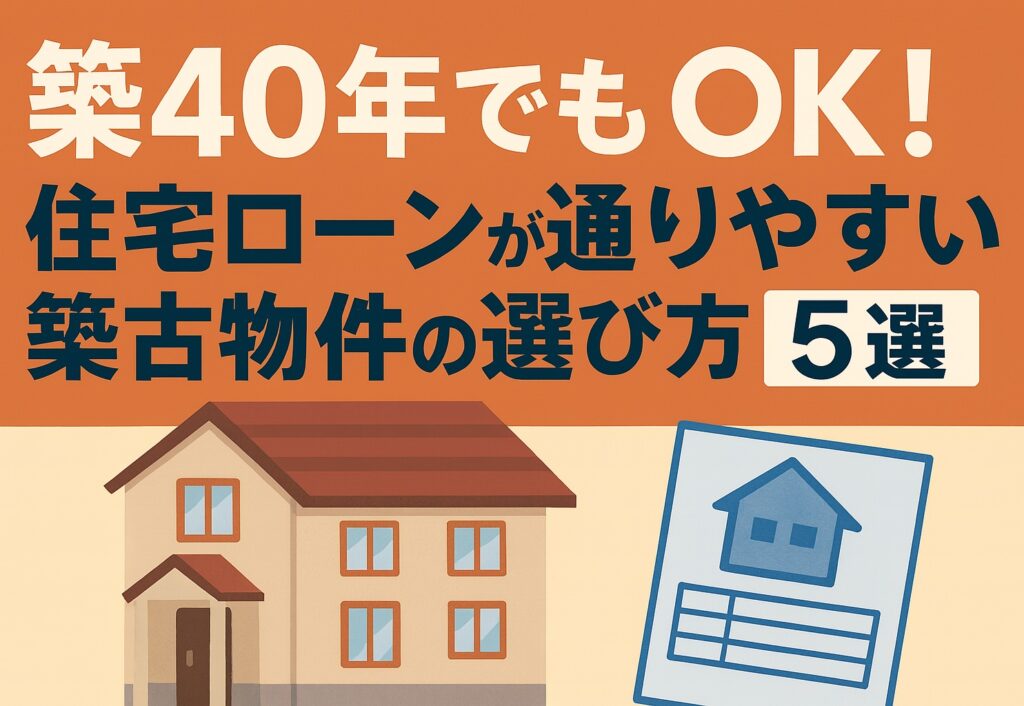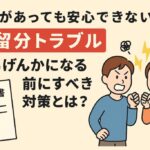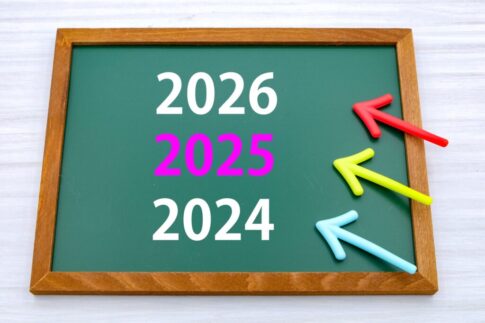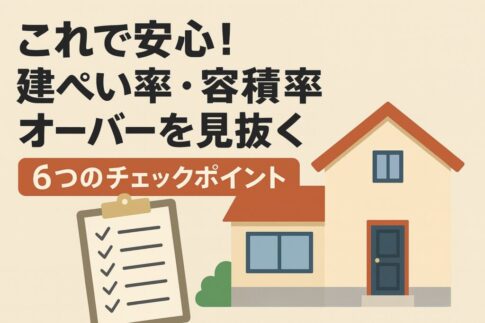皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
「築年数が古い家って、住宅ローンが通るの?」
中古住宅の購入を考えたとき、多くの人がまず不安に感じるのが、この“ローンが組めるのか”という点です。
実際、金融機関によっては「古すぎて担保評価が出せない」といった理由で、ローン審査に通らないケースもあります。
でも、築年数だけであきらめるのはもったいないです。
例えば、同じ築40年でも、ある物件はスムーズにローンが通り、別の物件は通らない…そんな違いが生まれるのはいったいなぜでしょうか?
不動産業界では、「築年数より立地・構造・状態が大事」とよく言われています。
このポイントを押さえるだけで、築40年でも問題なくローンが通る可能性は十分あります。
そこで本日は、住宅ローン審査が通りやすい築古物件を選ぶための5つのポイントについて話してまいります。
築古物件の購入を検討している方は、ぜひこの記事を参考に、ローンに強い物件を選んでください。
目次
築古でも住宅ローンが通る!その理由とは?
築年数だけが審査基準じゃない
住宅ローンの審査では、「築年数」は確かにひとつの要素です。
しかし、それ以上に重視されるのが「土地の担保評価」「建物の構造」「リフォーム可否」などの総合的な条件です。
銀行が見る“担保価値”のポイント
金融機関が見ているのは、この物件が将来も資産価値を保てるかどうかです。
築年数が古くても、建物の状態や立地条件が良ければ、しっかりと評価されて住宅ローンが通るケースは多くあります。

築40年でも住宅ローンが通りやすい物件の選び方5選
①「耐震基準適合」や「新耐震基準」クリア物件を選ぶ
昭和56年(1981年)6月以降に建てられた住宅は、新耐震基準に基づいている可能性が高く、住宅ローンの審査でも比較的評価されやすい傾向があります。
一方で、旧耐震の住宅であっても、耐震補強工事を行い「耐震基準適合証明書」を取得することを前提とすれば、ローン審査に通るケースも十分にあります。
現在、高知県内では、耐震診断・耐震改修工事に使える補助金制度が充実しています。
安全性を高めたうえで、内装や設備のリフォームも進めやすく、築古住宅でも安心して購入・活用を検討できます。
✅ポイント:築年数だけでなく「耐震性」に注目!
②「立地のよい場所」に建っている物件
住宅ローンでは、建物の価値よりも土地の担保評価が重視される傾向があります。
そのため、交通の便がよい・商業施設や学校が近いなど、立地条件のよい場所にある物件は、評価が高くなりやすく、ローン審査にも通りやすくなります。
✅ポイント:周辺の生活利便性(駅・スーパー・学校・病院など)はどうか
③「鉄骨造」や「RC造」の構造を選ぶ
木造よりも耐久性・耐震性が高いと評価される構造です。
築年数が古くても、鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)は、ローンが通りやすくなります。
✅ポイント:築40年でもRC造であれば、残存価値が見込まれる
④「リフォーム済み」または「リフォーム計画が明確」な物件
リフォーム前提の物件なら、「一体型ローン(リフォーム+住宅ローン)」がおすすめです。
金融機関も、「快適に住める状態か」を評価材料にしています。
✅ポイント:リフォーム業者の見積書を準備しておくと、ローン申請がよりスムーズに

住宅ローンとリフォームローンの違いは?
| 項目 | 住宅ローン | リフォームローン |
|---|---|---|
| 主な目的 | 住宅の購入 | 改修・修繕・内装変更など |
| 金利 | 比較的低い(年1〜2%台が多い) | やや高め(年2〜4%台が多い) |
| 借入金額 | 数千万円規模まで可 | 一千万円が上限のことが多い |
| 担保 | 必要(物件を担保に) | 基本的に無担保(信用力審査) |
| 審査 | 詳細・厳しめ | 比較的スピーディー |
| 控除制度 | 住宅ローン控除の対象 | 控除なし(※条件により例外あり) |
✅ポイント:築古+リフォームが必要な場合は、「一体型ローン」のほうが金利も低く、税制優遇も受けられます。
⑤「フラット35」など、築古でも使えるローン制度を上手に活用
フラット35は、築年数よりも「住宅性能評価」や「維持管理状況」を重視しています。
✅ポイント:古い家の性能を活かしたリノベ向きローンを上手に使うのがコツ
高知県の安芸市と中土佐町では、子育て世帯やUIJターンを対象に、下記①②の両方を併用できる体制が整備されています。
- フラット35地域連携型(子育て支援・地域活性化)による当初5年間の金利引き下げ(0.25~0.5%ほど)
- 自治体独自の補助金制度(例:空き家改修補助、新婚・子育て世帯向け補助など)

築古物件の購入を成功させる3つのアドバイス
事前に複数の金融機関に相談する
住宅ローンの審査基準や物件の評価は、金融機関によって異なります。
そのため、ひとつの金融機関だけで判断せず、複数の金融機関に相談して比較することが大切です。
とくに築年数が古い物件の場合は、過去に同様の物件で融資実績があるかどうかも確認しておくと安心です。
インスペクション(既存住宅状況調査)を検討する
住宅の安全性や修繕の必要性を事前に把握できるインスペクション(既存住宅状況調査)は、住宅ローン審査において金融機関からの信頼を得るうえでも効果的です。
調査には一般的に5万〜7万円程度の費用がかかりますが、「建物の状態に安心感がある物件」として評価されやすくなるため、ローン審査の通過率アップや購入後の想定外の修繕リスクを避けるといった点で、その費用を上回るメリットが期待できます。
「住宅ローン控除」などの制度もチェック
築年数が古い住宅でも、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」などの減税制度を活用できる場合があります。
例えば、耐震基準を満たすことや、購入後に所定のリフォームを行うことなどが要件となります。
これらをクリアすれば、年末のローン残高に応じた所得税の控除を受けることができ、最大で数十万円以上の節税効果が期待できます。
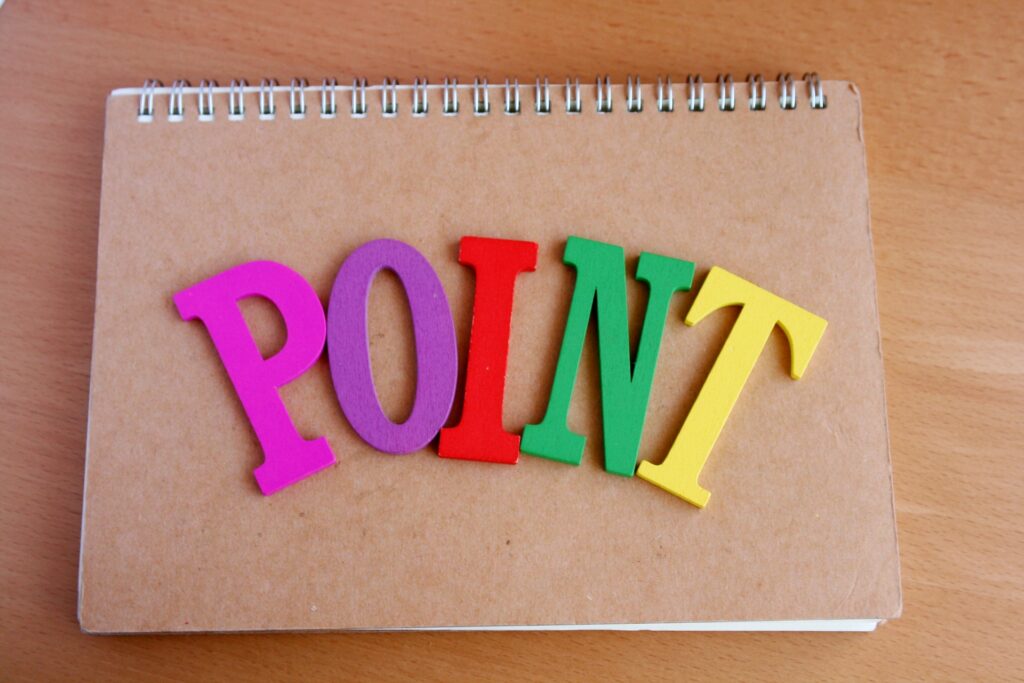
まとめ|築古でも“見るべきポイント”を押さえれば、住宅ローンは通る
築40年でも、住宅ローンが通る物件は少なくありません。
ポイントは「築年数」だけにとらわれず、「土地の立地条件」「建物の構造」「リフォームの計画」「耐震性」の4つをしっかりチェックすることです。
この4つの視点を押さえて物件を選べば、築年数が古くても安心して購入を進めることができます。