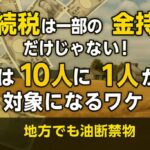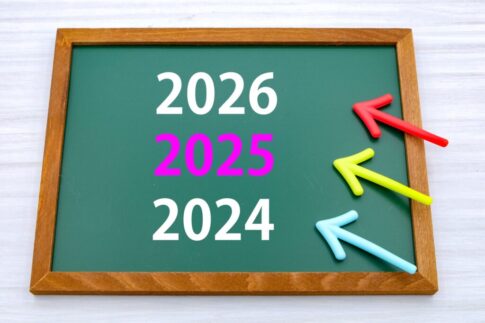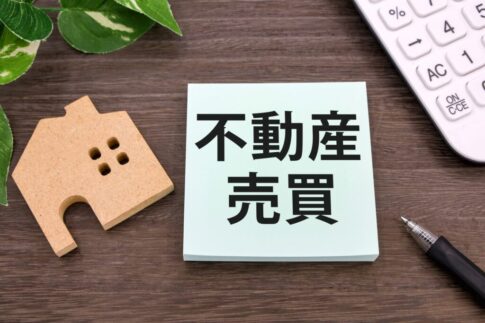皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
「相続した土地や家が売れない」「維持費だけがかかって毎年赤字」そんなお悩み、ありませんか?
実は今、使い道のない不動産が“負の資産”として重荷になっている人が全国で急増しています。
「手入れしていない山林」「耕作放棄された農地」「ボロボロの空き家」などは、所有するだけで税金・管理の負担がのしかかってきます。これはあなただけではありません。
このような「負動産」は、実質的に無償で譲渡する方法や、相続土地国庫帰属制度を使って国に引き取ってもらう選択肢があり、うまく活用すれば、次の世代に負担を残さずに不動産を手放すことができます。
そこで本日は、「無償譲渡」と「相続土地国庫帰属制度」で不動産を手放す方法について話してまいります。
目次
負動産とは?
「負動産」とは、持っているだけで損をする不動産のことです。
誰も住まない家や、使い道のない土地には、毎年の固定資産税・草刈り・管理費・老朽化による修繕・災害のリスクなど、コストがかかるばかりです。
にもかかわらず売れない、貸せないとなると、資産ではなく負債になってしまいます。
例えば、山あいの土地を相続したがアクセスが悪く、建築もできない。売りにも出しているが問い合わせはゼロ。
それでも毎年2万円の税金と草刈り業者への支払いが必要。
土砂崩れで下の家に被害が出ないか心配。
このような「持っているだけで損をする不動産」こそが、今まさに問題視されている“負動産”です。

無償譲渡で欲しい人に引き取ってもらう
活用意欲のある人に「無償」で不動産を譲ることで、維持費や管理責任から解放される方法です。
売れない物件でも、「タダならほしい」という人は一定数います。
とくに田舎暮らし希望者やDIY愛好家、事業目的の方などは、費用をかけてでも活用したい場合があります。
高知県のある空き家では、老朽化が進んでいたため売却価格はゼロ。
解体費用も高くつくため所有者は困っていました。
そこで0円物件として、引き取り手を無料広告の掲示板「ジモティー」で募集したところ、「リフォームして貸家として活用したい」という不動産投資家からの申し出があり譲渡が成立。
結果、所有者は維持費と管理責任から解放されました。
無償譲渡の進め方
- インターネットを利用して引き取り手を募集する
- 譲渡の条件はしっかりと伝える
- 通常の不動産売買と同様に、重要事項説明書や売買契約書を作成し、所有権移転登記(名義変更)を行う
相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう
条件を満たせば、国に土地を引き取ってもらえる制度があります。
2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地について、一定の要件をクリアすれば、所有権を手放して国庫に帰属させることが可能です。
これで今後の維持管理費や責任から解放されます。
最近では、山林や畑のような使う予定のない土地を相続した方が、維持費や将来の管理負担を心配して申請を行いました。
登記整理や書類作成などの手間はかかりましたが、条件を満たしていたため、審査を経て約1年後、無事に土地を国に引き渡すことができました。
無償譲渡で引き取り手が見つからなくても、最終的に国へ返すという選択肢があることは、大きな安心につながります。
相続土地国庫帰属制度の主な条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建物がない土地であること | 建物がある場合は、解体して更地にする必要あり |
| 境界トラブルがないこと | トラブルがあれば境界確定が必要 |
| 土地に問題がないこと | 土壌汚染、災害が発生する恐れがある崖地、未接道地などはNG |
| 土地に担保・抵当権がないこと | 登記簿上の権利関係をクリアにする必要あり |
| 費用の負担 | 事前審査手数料(14,000円)+負担金(面積に応じて20万円~) |
どちらを選ぶべき?比較と判断のポイント
| 項目 | 無償譲渡 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 費用 | 原則無料 | 審査手数料 14,000円・負担金 20万円~ |
| 所要期間 | 数週間~ | 申請〜完了まで1年程度 |
| ハードル | 相手を探す必要あり | 条件・審査がある |
| 利用タイミング | 生前・相続後どちらも可 | 相続後のみ |
| 向いているケース | 売却を諦めた物件 | どうしても引き取り手がいない物件 |
まとめ|無償譲渡と相続土地国庫帰属制度は“同時進行”がおすすめ
負動産をできるだけ早く、かつ費用を抑えて手放したい場合は、「無償譲渡」と「相続土地国庫帰属制度」を同時に進めるのが効果的です。
それぞれの方法の最大の違いは、「手放せるまでのスピード」と「費用負担」です。
- 無償譲渡は、相手さえ見つかれば数週間で完了し、費用負担ゼロも可能
登記には数万円の費用がかかりますが、その費用をすべて引き取り手に負担してもらうことも可能です。 - 国庫帰属制度は、申請から承認まで1年以上かかることもあり、負担金がかかる
申請時には審査手数料14,000円が必要で、原則として1筆あたり20万円の負担金は、審査が通った後(目安として約1年後)に支払います。
国庫帰属制度を申請中であっても、無償譲渡などで引き取り手が見つかった場合は、申請を取り下げることが可能です。申請から承認までには1年以上かかるケースもあるため、時間や費用のロスを防ぐためにも、譲渡先探しと制度申請を同時に進めることをおすすめしています。
※なお、申請時に支払う審査手数料(14,000円)は、申請を取り下げても返金されませんのでご注意ください。

不動産処分の手順
✅不動産の現状を確認する
まずは、現在の不動産の状態を整理しましょう。
登記内容や所有者名義、隣地との境界、建物の有無や老朽化の程度などを把握することで、譲渡や制度申請に必要な準備が明確になります。
✅譲渡に向けた情報をまとめる
譲渡を検討する場合は、相手に伝える情報をあらかじめ整理しておくことが大切です。
所在地、土地や建物の面積、写真、周辺環境、アクセス情報、注意点などをひとつの資料にまとめておくと、引き取り手とのやりとりもスムーズになります。
✅インターネットで情報発信をする
「欲しい人」に出会うには、物件の存在を知ってもらうことが第一歩です。
空き家バンク、ジモティー、SNS(XやInstagram・Facebookなど)、譲渡サイトを活用して、写真付きで物件情報を発信しましょう。
✅国庫帰属制度の要件をチェックする
土地を国に引き取ってもらいたい場合は、相続土地国庫帰属制度の要件に合うかどうかを確認しましょう。
建物の有無、境界の状況、土地の状態(崖地・土壌汚染・接道状況など)をチェックし、制度の公式サイトや資料をもとに判断することが大切です。
✅法務局に相談し、申請に向けて動く
要件をクリアできそうであれば、最寄りの法務局に相談し、申請に必要な書類や流れを確認しましょう。
申請時には審査手数料14,000円が必要となり、審査を通過すれば負担金(原則20万円)を納付して土地の所有権を手放すことができます。
どちらか一方ではなく、両方の準備をしておくことで、負動産を手放すための選択肢が広がります。
時間も費用も無駄にせず、次の世代へ負担を残さないためにも、今できることから始めましょう。