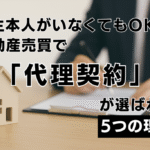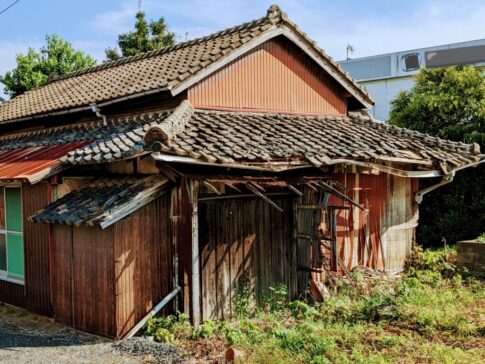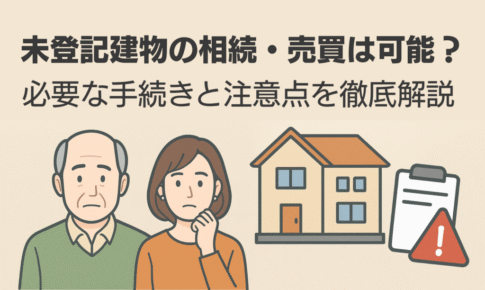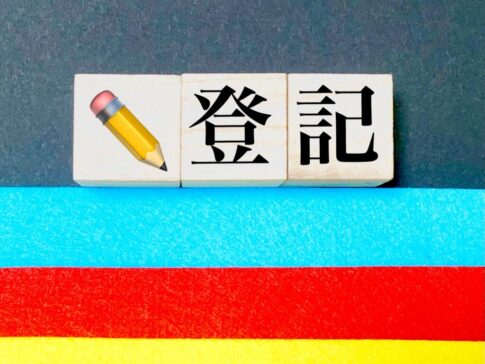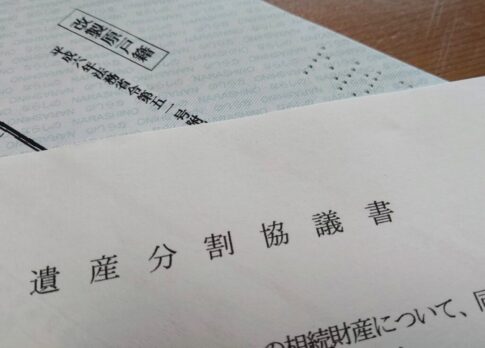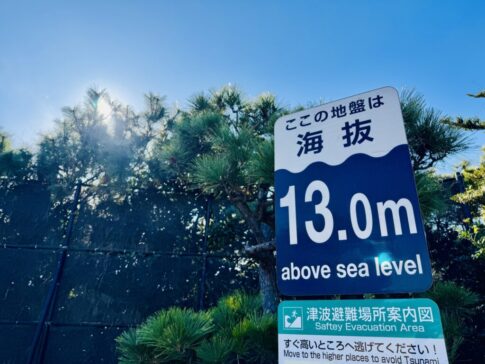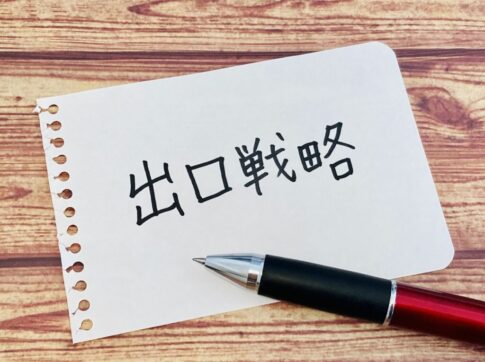皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
相続した不動産を売却しようとするとき、多くの方がまず気にされるのが「税金はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。
「不動産の税金は高そう…」という漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。
しかし実は、相続や売却の際に使える税制特例が数多く用意されており、これらを正しく活用すれば、税負担を大きく軽減し、手元に残るお金を増やすことが可能です。
そこで本日は、相続した不動産を売却する際にぜひ知っておきたい「税制特例(2025年度版)」について話してまいります。
知らないと損をするかもしれない税制特例、ぜひこの記事を最後までお読みください。
目次
そもそも「譲渡所得税」とは?相続後の売却にかかる税金の基本
譲渡所得の仕組み
不動産を売却すると、その売却益(利益)に対して「譲渡所得税」が課されます。相続した不動産であっても、売却によって利益が出れば課税対象です。
計算方法
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、元の所有者がその不動産を取得した際の金額です。
相続の場合、この「取得費」が不明になることが多く、結果として税負担が大きくなることもあります。
譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかる「必要経費」のことです。
例えば、不動産会社への仲介手数料、残置物の処分費用、土地の測量費、登記手続きにかかる費用などが、譲渡費用として認められます。
取得費が不明な場合の「5%ルール」
もし取得費がわからない場合は、売却金額の5%を取得費とみなすことになります。
例えば、1,000万円で売却した場合、取得費は50万円と計算されます。
注意点として、このルールを使うと本来の取得費よりも少なく見積もられることが多く、結果的に譲渡所得が多くなり税額が高くなります。
特例との関係
この課税対象となる譲渡所得を圧縮できるのが、各種「特例」です。

2025年度版|相続不動産の売却で使える主要な税制特例一覧
1. 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除され、所得税・住民税が大幅に軽減されます。
2. 小規模宅地等の特例(※売却前に相続税評価額を下げる)
相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
売却自体ではなく「相続時点の評価額」に効く特例ですが、結果として譲渡時の税負担軽減にも寄与します。
3. 取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その一部を不動産の取得費に加算することで、譲渡所得を圧縮できます。
相続から3年以内の売却が条件です。
4. 居住用財産の3,000万円特別控除
被相続人が亡くなる前に住んでいた家を、相続人が一定期間内に売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。
空き家特例と似ていますが、条件が異なります。
| 比較項目 | 居住用財産の特別控除 | 空き家の特別控除 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大3,000万円 | 最大3,000万円 |
| 対象者 | 売主自身が居住していた不動産 | 相続で取得した空き家 |
| 必要な居住要件 | 相続人が一定期間住んでいた場合など | 被相続人が一人暮らしで住んでいた |
| 建物の条件 | 特になし | 昭和56年5月31日以前の旧耐震住宅が対象(※買主による耐震改修が必須) |
| 適用タイミング | 原則、売主が住んでいた家を売るとき | 相続後、空き家を売却するとき(3年以内) |
5. 譲渡損失の損益通算・繰越控除
売却損が出た場合、給与所得など他の所得と相殺できる制度です。
条件を満たせば、翌年以降3年間繰り越し控除も可能です。
6. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
都市計画区域内にある低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得から最大100万円まで控除できる制度です。
相続不動産の中でも使われていない空き家や空き地などが対象になります。

特例を使うための条件・注意点
条件の違いに注意
- 空き家特例:旧耐震+一人暮らし+相続後3年以内の売却
- 取得費加算:相続税納税+3年以内の売却
- 小規模宅地等:相続税申告期限までの適用申請
- 低未利用土地:自治体の証明+譲渡価格500万円以下などの条件
- 5%ルール:取得費が不明な場合
複数の特例の併用はできる?
一部の制度は併用可能ですが、「空き家特例と居住用3,000万円控除」は併用できないなど、組み合わせに制限があります。
具体的にいくら違う?特例を使った場合の税額シミュレーション
ケース1:空き家特例を使った場合
- 売却益(譲渡所得):1,000万円 → 約203万円課税(所得税・住民税)
- 控除:3,000万円 → 税額ゼロ
ケース2:取得費加算の特例を適用
- 売却益(譲渡所得):1,000万円 → 約203万円課税
- 相続税100万円を取得費に加算 → 実質的に課税所得が900万円に圧縮約 → 約183万円課税
ケース3:特例を使わなかった場合(5%ルール適用)
- 売却価格:1,000万円
- 取得費(概算):50万円(1,000万円×5%)
- 売却益(譲渡所得):950万円 → 約195万円課税

特例を使いこなすコツ|売却前にやっておくべきこと
1. 物件の状況確認(空き家・耐震・使用状況)
空き家特例などは建物の耐震性や居住履歴が重要な判断基準になります。
2. 相続登記を完了させる
不動産を売却するには、まず相続人への名義変更=相続登記を行うことが必要です。
3. 専門家に相談して節税戦略を立てる
「どの制度が使えるのか」「どこまで申告が必要なのか」など、税理士・不動産会社へ相談を。
まとめ|制度を使えば“数百万円”の節税も可能。まずは確認から
- 相続不動産の売却には、複数の税制特例がある
- 制度を使えば大幅な節税が可能だが、条件や期限が複雑
- 損をしないためには、早めに調べて準備を進めることが重要