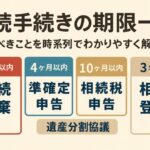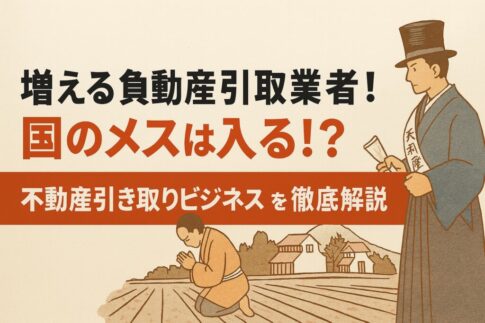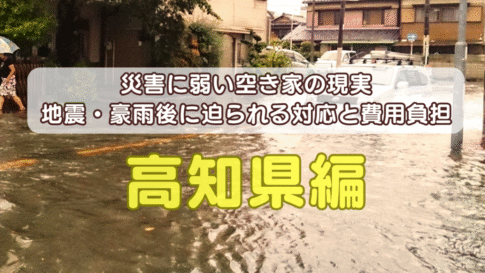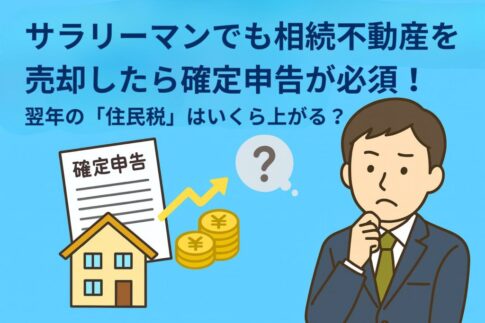皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
アパート経営は築年数が古くなるにつれて、空室が増えたり修繕費がかさんだりと、悩みが尽きなくなります。
「このまま持ち続けて大丈夫なのか…」と不安を感じるオーナーも少なくありません。
老朽化や空室率の増加など“築古アパート問題”は全国的な課題となっており、国も対策を進めています。
そこで本日は、相続した築古アパートを「売るべきか?活用すべきか?」と迷っている方に向けて、それぞれの選択肢について話してまいります。
目次
築古アパートはなぜ“負動産”と呼ばれるのか?
築古アパートは、賃料収入よりも維持コストの方が大きくなりやすく、所有しているだけで損をする「負動産」と言われることがあります。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 空室率の増加 | 設備が古く、入居者が集まらない |
| 修繕費の増加 | 給排水管、屋根、外壁など、大規模修繕が必要 |
| 家賃の下落 | 築年数に比例して、賃料は下がる傾向にある |
| 管理負担 | トラブルやクレームへの対応が増える傾向にある |
| 税金負担 | 空室でも固定資産税はかかり続ける |
例えば、築50年の木造アパートで6戸中5戸が空室、唯一の入居者からの家賃は月3万円。
老朽化による修繕費や管理費、固定資産税などを差し引くと、毎月赤字になってしまいます。
このような状況になると、「このまま持ち続けるのは負担だな」と感じる方も多く、売却を真剣に検討するケースが増えてきます。

売却するメリットとデメリット
収益が出ない築古アパートは、思い切って売却することで「赤字からの解放」と「現金化」が可能です。
メリット
- 赤字経営から脱出できる
- 維持費・固定資産税から解放
- 管理や修繕のストレスがなくなる
- 現金化して別の用途に使える
デメリット
- 築古だと買い手がつきにくい
- 売却価格が「土地値以下」になることも
- 修繕しないと売れない場合がある
- 売却益に譲渡所得税がかかることも
売却のコツ
- 買主の対象を広げる
- 更地にして売るかどうかの判断
- 空室対策をしてから売り出す
- そのアパートを本当に必要としている人に出会えれば、“負動産”は“資産”に変わる

活用して再生する方法は?
築古アパートでもターゲットを明確にすることで収益化する道があります。
具体的な活用方法
| ターゲット | 概要 |
|---|---|
| 外国人労働者向け | 働く外国人に特化した賃貸。家財道具付き、Wi-Fi完備など、文化や生活習慣の違いに配慮した住環境を提供します。今後ますます需要が高まります。 |
| 住宅確保要配慮者向け | 高齢者・低所得者・ひとり親世帯など、住宅確保が難しい方に向けた賃貸。自治体の協力を得て、安定した入居と長期的な賃貸経営を目指せます。 |
注意点
- 国や自治体のルールに従う必要がある
- 社会的な意義も踏まえた視点が求められる
売却と活用、どちらを選ぶべき?
「立地・建物の状態・ご自身の理想」を総合的に判断しましょう。
| 判断基準 | 売却を検討すべき人 | 活用を検討すべき人 |
|---|---|---|
| 空室率 | 長期的に高い | 一時的な問題なら活用可能 |
| 修繕状態 | 雨漏り・故障などが多い | 軽微な修繕で済む |
| 自己資金 | 修繕費を出せない | 初期費用を出せる |
| 理想 | 手間のかかる賃貸経営から解放されたい | 今後も安定した家賃収入を得続けたい |

まとめ|築古アパートが“負動産”かどうかは、活用方法と気持ち次第
「古いからもうダメ」と決めつける前に、一度立ち止まって選択肢を見直してみましょう。
自分にとっての“理想のかたち”が、意外なところに見つかるかもしれません。
- 少しの工夫と行動で、“負動産”が“収益物件”に生まれ変わる可能性も十分にある
- 売却を考えるなら、できるだけ早めに動くことが成功のカギ
- 放置していると、税金・老朽化・近隣トラブルといったリスクが拡大していく